 |
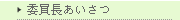 |
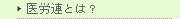 |
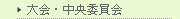 |
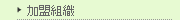 |
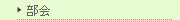 |
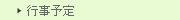 |
 |
 |
 |
 |
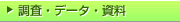 |
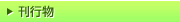 |
 |
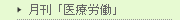 |
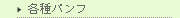 |
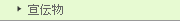 |
 |
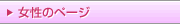 |
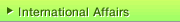 |
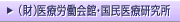 |
 |
 |
 |
 |
 |
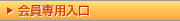 |
 |
 |
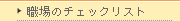 |
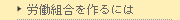 |
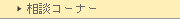 |
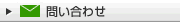 |
 |
日本医療労働組合連合会
〒110-0013
東京都台東区入谷1-9-5
日本医療労働会館3F
TEL03-3875-5871
FAX03-3875-6270
地図はこちら |
|
|
|
|
 |
 |
| 「看護の日」ナイチンゲールの思いは受け継がれているか? |
 |
慢性化する長時間労働に疲弊する現場
小林美希
5月12日は「看護の日」。フローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで1991年に旧厚生省によって制定された。今年で20年の節目となる。
看護師、保健師、助産師、准看護師を指す「看護職」は、全国で約133万人が働いている。女性労働者の20人に1人が看護職という女性の代表的な仕事とも言え、看護職の95%を女性で占める。看護師に憧れたり、「手に職をつけて、一生働きたい」「経済的に自立したい」と看護の世界に足を踏み入れた女性も少なくない。
ここ数年は、男性看護師も増加している。看護職の中でも、看護師の数は2006年で84万8185人。男性看護師に限ると、1998年の1万7807人から2006年には3万8028人と倍増している。
ところが、看護の現場では、過酷な労働を余儀なくされ、離職が止まらない。看護職の免許を持ちながら実際には働いていない潜在看護職員は55万〜56万人と推計されている。過重労働の重責は、男女の関係なく、のしかかっている。
制度上、人員増が実現しにくい
「確かに女性より体力があるかもしれないが、男にとっても、あまりの激務。この先、看護師を続けていけるか自信をなくしているところ」
ある自治体病院(600床以上)のオペ(手術)室で働く杉田直也さん(仮名、30代前半)は、嘆く。オペ室勤務になってから4年が経つ。ところが、休暇の日も、病院からの呼び出しに迅速に対応しなければならないオンコールがある。このため、2〜3週間、全く休みなく働くこともしばしばだという。
近隣に大学病院があるが、直也さんが働く病院は地域の中核病院として、救命救急センターへの搬送も頻繁に受け入れている。大学病院のオペ室は看護師が50人ほど配置されているというが、直也さんの病院ではその半分くらいの人員で大学病院の手術件数に匹敵する年間6000件もの手術を引き受けている。
当然、看護師の負担は増しており、「昨日1日でも40件ほどのオペがあった。予定しているオペのほかにも緊急オペが2〜3件入ることもよくある。うちは看護師1人が年間200件ほどオペに入り、業界で適正と言われる1人当たりが受け持つ手術件数をはるかに超えている」(直也さん)という。
病院は救急医療の充実を全面に打ち出しており、目下、看護体制も、一般入院基本料では最高の看護配置基準「7対1」(患者7人に対し看護師1人)を採ろうとしている。
しかし、オペ室の人員配置は手薄いまま。増員を求めても、経営側は首を縦には振らない。なぜなら、診療報酬の中で看護師の業務に関しては独立した保険点数がなく、一般病棟での入院基本料の看護配置でしか看護師が評価されていないからだ。すると、経営側から見れば「オペ室や外来などの看護師は保険点数に結びつかない」ということで、人件費をギリギリのところで抑えようとする傾向が強くなる。
そうした経緯から外来はほとんどの病院で看護師のパート化が進んでいる。一方で、極めて専門性の高いオペ室は正職員でなければいけないためパート化はできず、人件費増を抑制するために余裕をもった人員配置が行われないのだ。
オペ室は、2交代制勤務や医師のように当直制が導入されていることが多いが、直也さんの病院では3交代を採っている。日勤は午前8時30分から始まり午後5時30分までだが、手術が午前9時から始まるのであれば始業の1時間ほど前から出勤して準備しなければならない。夕方以降も手術が残っていれば午後9時頃まで残業したり、深夜0時までオペ室に居続けることも少なくない。
深夜、人手が少ない中で緊急オペが入れば、そのまま朝まで、時にはそのまま翌日の日勤に入り午後6時頃までと34時間連続で働き続けることもある。帰宅できても、夜勤の時間帯は、毎日がオンコール体制で、常に病院からの緊急呼び出しに備え待機していなければならず拘束される。いつ呼び出しがかかるか分からない緊張が続く。日勤の日に深夜0時を越えて残業が発生した場合、さすがに翌日の午前中は休めるが、年次有給休暇を使っての休日という矛盾の中にいる。
医療現場ではどこの部署も重要だが、オペ室でのミスは決して許されない。常にピリピリとした状況のうえに睡眠不足が加わると、直也さんはどうしてもイライラしてしまうという。
いったい何時に仕事が終わるのか先が見えない。「せめて、休みがあれば・・・」。同じように不規則のはずの病棟の看護師でさえも、オンコールがない分、羨ましく思えてしまう。直也さんは「運良く月に4〜5日休みが取れたとしても、体を休めないといけないから、気晴らしできるのは1日か2日。ストレスは全く発散できない」と諦め顔だ。プライベートな生活はないに等しい。
直也さんは「仕事は好きだし、やりがいも感じている」。しかし、いくら好きな職業でも、超長時間・過重労働に陥っては心身ともに燃え尽きる。「日勤(午前8時30分から午後5時30分)、準夜勤(午後4時30分から翌日午前1時15分)、遅番(午後0時30分から午後9時15分)、日勤(午前8時30分から午後5時30分)」というシフトで、時間通りに終わることはなく、延々と仕事が続き、過労死も他人事ではない。
20代の看護師でも、疲労でふらふらと倒れそうになりながら働いている。2008年10月に、労働基準監督署が都内で働く20代の看護師の過労死認定を行ったことは記憶に久しくないが、亡くなった女性はオペ室の看護師だった。
「体調を崩して休みたくても、1人でも抜けると回らないので良い顔をされず休めない。這ってでも出勤する。体力はあるほうだが、さすがに限界が来る」という直也さん。「看護師を辞めて、コーヒーショップでも開いてみたい」と、ぼんやり考えてしまうという。
看護職員の「慢性疲労」は7割以上
男性看護師は体力があるからと、オペ室やICU(集中治療室)、外科病棟や精神科病棟など病院の中で、比較的ハードな分野に配置されることが少なくない。患者が暴れたりする時も、男性看護師の出番となることが多い。病院は女性が多い職場であるため、妊産婦の代わりに夜勤に入るなどフォローしてくれる強い味方にもなるのが男性看護師でもあるのだが、過重労働以外の悩みも抱え、「看護師ならではの、看護しながら治っていく過程を見るような“療養上の世話”というやりがいを実感できないことが残念」という側面もある。
そして賃金面も労働の対価に見合うとは言い難い面がある。直也さんの病院では、10年目の中堅となっても、休みなく昼夜問わずに過労死寸前まで働いた年収は手取りで400万円程度。公務員の定数削減のトレンドがある中で、賃金が上がっていく期待はしづらい。
民間病院では、自治体病院より低賃金という実態もある。「きっと、まだ女性の労働という風潮があり、いつまでも賃金が低く抑えられているのだろう。女性の一般的な職業よりは少しは賃金はいいのだろうが、男性が家計を支える、寝ずに患者の命を守るといった点からは十分な報酬とはいえない」と、労働条件の面でも長く勤められるか、直也さんの不安は隠せない。
日本医療労働組合連合会が2009年11月〜2010年1月にかけて行った「看護職員の労働実態調査」の中間報告(2010年4月公表)から、看護職員の過酷な労働実態や健康不安が浮かび上がった。3交代勤務の中で、夜勤が1カ月平均で9回以上というケースが3割を超えている。その日の勤務と次の勤務との間隔が「6時間未満」が3割を超え、「12時間未満」は75%にも上る。
往復の通勤時間を考えれば、睡眠時間の確保は不十分な状態となる。2交代制では、夜勤が16時間以上となるケースが53%。そうした長時間に渡る夜勤回数が1カ月で5回以上が37%という状態だ。休息時間を取れないことが準夜勤で目立ち、「全く取れていない」(6.9%)、「あまり取れていない」(44.1%)を合わせると半数を超える。
同調査では、看護職員の健康について「慢性疲労」が7割を超え、「健康に不安」という声は6割を超えている。自覚症状として、「全身がだるい」(52.4%)、「腰痛」(49.7%)がほぼ半数を占め、「なんとなくイライラする」(40.8%)、「根気が続かない」(29.4%)、「憂鬱な気分がする」(37.8%)と精神的な症状を訴えている。当然、看護職の薬の常用が増え、鎮痛剤、胃腸薬、ビタミン剤などを6割が常用しており、中には睡眠剤や安定剤を飲みながら勤務している看護職もいる。
こうした状況では、特に女性の場合、妊娠期に深刻な問題に直面する。公的病院や民間病院、病院規模を問わず「人手不足で妊娠したからといって夜勤は免除されなかった。流産しかかっても、お腹の張り止めの薬を飲みながら働き、いよいよ出血が止まらず流産の危険が高くなってからは入院し、退院するとまたすぐ現場に戻らされた」と、無理をして流産するケースは全国で多発している。
前述の調査からも、看護職の切迫流産(流産しかかる状態)が年々増加しており、1988年の24.3%から2009年は34.3%となった。つまり、3人に1人が切迫流産を経験していることになる。流産は、1988年の7.5%から2009年は11.2%に増加した。つわり、出血、むくみ、蛋白尿を訴える割合も増えている。
命を預かり、また、新たな命を世に送り出すはずの医療の現場で、そこで働く看護師自身に授かった命が奪われている。その働き方は、前述した直也さんと変わらない。若手の男性でも過労死寸前という中で、妊産婦が安全に働くことができるはずがない。
社会として看護師のバックアップが必要
看護師そのもののワークライフバランスはもちろんだが、それだけではなく、その家族のワークライフバランスを考える必要がある。家族を形成していこうと思った時に、パートナーの働き方が硬直的では、家事や子育ての負担が偏ってしまう。結局は、どちらかが辞めるという選択を強いられることになり、本当の意味での両立は実現しない。
日本看護協会の小川忍常任理事は「看護師の95%は女性。そのパートナーとなる男性のワークライフバランスが実現しなければ問題は解決しない。社会全体のワークライフバランスの実現に向き合うべきだ」と指摘する。
日本看護協会の調査によれば、潜在看護職員の離職理由のトップは「妊娠・出産」(30.0%)で2位が「結婚」(28.4%)、3位が「勤務時間が長い・超過勤務が多い」(21.9%)、4位「子育て」(21.7%)、5位「夜勤の負担が大きい」(17.8%)と続き、上位10位の中には、「自分の健康」「責任の重さ・医療事故への不安」も入っている。
看護師の労働環境の厳しさは、それだけではない。小川常任理事によれば「看護師には業務上の危険がたくさんある。結核や肝炎などの感染リスクを抱え、医療機器や材料の使用、医薬品などへの曝露というリスクと常に背中合わせ。医療を支える看護師を社会全体でバックアップしなければいけない」と話す。
看護職は、日勤だけでなく夜勤もこなし、患者の命を預かる社会的に重要な職務をしている。それだけでなく、本来ならあるべきでない残業に明け暮れ、研修も受け、看護研究もしている。それに加えて、家事や育児の負担まで抱えるのでは、バーンアウトして辞めてしまっても当然だ。
冒頭のようにここ数年、男性看護師が増加した中には、不況に左右される製造業などの異業種から安定を求めて転身するケースもある。看護の業界にやりがいを感じつつも、過重労働に限界を感じて人材が去っていくことは防がなくてはいけない。患者と常に接する看護師の観察によって、異変に気づき、助かる命はたくさんある。
いつ自分や家族、友人や恋人が事故に遭うか、いつ病気になって手術が必要になるか、それは予測できないこともある。その時、看護師が疲れ切っているのでは、患者にとっても不幸であることは言うまでもない。
ダウンロードはこちら(word)→「看護の日」ナイチンゲールの思いは受け継がれているか?
リンクはこちら→日経オンラインビジネス
|
|
|
|

